2022年11月23-24日
四国の高知城と宇和島城を訪れることができたので、現存十二天守の残りは、備中松山城だけとなった。 ぜひ訪れたいとは思いつつ、遠方であることから、二泊三日ではきつい。 往復の高速代の割引を考えると、水曜から土曜の三泊四日であれば、帰宅した翌日が休養日に充てられる。
そんな組合せが、11月にあった。兵庫岡山付近で計画していたところ、奥さんが私も行きたいと言い出したため、 奥さんの希望も入れた日程となった。

<<書写山円教寺:摩尼殿>>
|
2022年11月23-24日 四国の高知城と宇和島城を訪れることができたので、現存十二天守の残りは、備中松山城だけとなった。 ぜひ訪れたいとは思いつつ、遠方であることから、二泊三日ではきつい。 往復の高速代の割引を考えると、水曜から土曜の三泊四日であれば、帰宅した翌日が休養日に充てられる。 そんな組合せが、11月にあった。兵庫岡山付近で計画していたところ、奥さんが私も行きたいと言い出したため、 奥さんの希望も入れた日程となった。 |
 <<書写山円教寺:摩尼殿>> |
 |
<<浄土寺>> なかなか行けない場所を、今回は計画に入れている。 浄土寺は、国宝の阿弥陀三尊像で有名なお寺である。 その阿弥陀如来が安置されている浄土堂も、併せて国宝になっている。 特に、西日が差し込んで屋内を照らすときには、お堂内部が黄金に輝いて、阿弥陀如来の来迎を思わせる景色になる。 今回も、一日目の最終として、夕方をねらって訪れることにした。 | ||||
  |
<<浄土寺:浄土堂>>
中央に阿弥陀如来像−高さは須弥壇から5.3m−。 両脇に勢至菩薩・観音菩薩の両脇侍像−高さは須弥壇から3.7m−。 いずれも、快慶作である。 仏像の脚部は須弥壇を突き抜け、地面にまで届いて固定されているという。 したがって、この像を外に出すことはできないのだそうだ。 この場所においてこその阿弥陀様というところか。 | ||||
  |
<<浄土寺:本堂(薬師堂)>> 永正14年(1517年)の再建。重要文化財。 再建前の建物は、浄土堂と同じ建久8年(1197年)の建立で、同規模同形式で、向き合って建てられている。 奈良時代に僧行基により開山された広渡寺が前身寺院とされる。 奈良の大仏再建に奔走していた重源は、その再興拠点として全国七か所に東大寺別所を創設した。 播磨の別所として当地を定め、荒廃していた広渡寺を移して浄土寺と改めて開山した。 薬師堂の本尊薬師如来は、広渡寺の本尊であったという。 <<浄土寺:開山堂>> 開山である重源上人の像が安置されている。 創建は不明。現在のお堂は、永正17年(1520年)の再建。 | ||||
 |
<<浄土寺:鐘楼>> 創建は不明。現在のものは寛永9年(1632年)の再建。 | ||||
 |
<<浄土寺:八幡神社拝殿>> 浄土寺の伽藍は、東西に薬師堂(本堂)と浄土堂が向かい合う形で建っている。 その真ん中を、南北に八幡神社の参道が貫いている。 八幡社は南面し、その前に拝殿がある。 拝殿は、中央に通路のある割拝殿の形式をとっている。 延応元年(1239年)創建。鎌倉時代後期の再建。重要文化財。 | ||||
 |
<<浄土寺:八幡神社本殿>> 文暦2年(1235年)創建。室町時代中期の再建。重要文化財。 八幡神社は、浄土寺創建時に建てられた鎮守社である。 | ||||
 |
<<浄土寺:板碑>> 古墳時代の石棺と同じ材料を用いて作られている。 一番右側の石は、幅約60cm、高さ約130cm、地蔵菩薩が刻されている。 | ||||
 |
<<浄土寺:芭蕉句碑>> 芭蕉作 寿しさは 飛騨の匠の 指図哉 すずしさは ひだのたくみの さしずかな 文化9年(1812年)建立。 | ||||
 |
<<書写山円教寺:書写山ロープウェイ山麓駅>> 円教寺は、書写山(標高371m)の山上にある。 山上に上るロープウェイがある。 ロープウェイは15分間隔で運行しているが、まだ時間が早いせいか駅も閑散としている。 ここのロープウェイの桟橋は、駅に到着すると左右両側から、挟むように緩衝材が出てきて、車体を固定する。 なんでも、日本で三基目に導入されたものだという。 | ||||
 |
<<書写山円教寺:山上からの眺望>>
| ||||
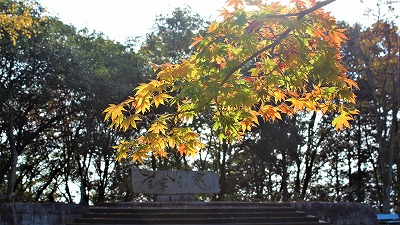 |
<<書写山円教寺:椎谷鱗三文学碑>> 椎谷鱗三は、当地(姫路市書写)出身の文学者。
| ||||
   |
<<書写山円教寺:慈悲の鐘>> ロープウェイの山上駅から摩尼殿まで、マイクロバスが運行している。 ほぼ、ロープウェイの運航と連動しており、待ち時間なく乗ることができる。 途中にも見どころはあるので、帰りは歩いて降りてくることにしよう。 「こころの鐘」と読む。 平成4年(1992年)建立。 ここで、徒歩の参道とバス道が分岐する。 <<書写山円教寺:仁王門>>
| ||||
   |
<<書写山円教寺:摩尼殿>> バスの終点が摩尼殿である。 西国三十三か所第27番札所 書写山円教寺。 書写山(標高371m)の山上に、西国三十三か所の中でも最大規模の伽藍を持つ、天台寺院である。 「西の比叡山」とも呼ばれ、寺格の高さを誇っている。 康保3年(966年)、性空の創建と伝えられる。 この堂の創建前、天人が桜樹を礼拝するのを見た性空が、弟子の安鎮に命じて、 根のあるままの生木に如意輪観音像を刻み、三権四方のお堂を建てた。 これが、摩尼殿のはじまりだという。 本尊を動かすことができないため、このような懸造りになったという。
本尊は、木造如意輪観音坐像。 昭和8年(1933年)石本暁海作。 <<書写山円教寺:はづき茶屋>> 摩尼殿の下にはづき茶屋が見える。 | ||||
 |
| ||||
 |
<<書写山円教寺:三之堂(みつのどう)>> 広場を囲んで、大講堂・食堂・常行堂の3棟が、コの字の形に並んでいる。 総称して三之堂という。 正面が食堂、右(北)側が大講堂、左(南)側が常行堂。 大講堂は、下層は永享12年(1440年)、上層は寛正3年(1462年)の再建。重要文化財。 食堂は、室町時代中期の再建。重要文化財。 常行堂は、享徳2年(1453年)の再建。重要文化財。 | ||||
  |
<<書写山円教寺:大講堂>>
<<書写山円教寺:常行堂>> 一見、どういう形なのか、よくわからない建物だった。 脇に回ると、こっちに正面があるのかといった感じ。 (写真は正面ではないらしい) 右側の入母屋造りの建物が本体で、五間四方、中央に阿弥陀如来座像が安置されている。 そこに、手前(北)側の切妻の建物が接続している。 右側を中門、左側を楽屋と言い、中央には、一間四方の舞台が張り出している。 この舞台は、大講堂の釈迦三尊に舞楽を奉納するために使うらしい。 | ||||
 |
<<書写山円教寺:弁慶の鏡井戸>> 食堂のわきに、小さな池というか井戸がある。弁慶の鏡井戸という。 書写山には武蔵坊弁慶が少年時代を過ごしたという伝説がある。 ある日、昼寝をしていた弁慶の顔に、同僚がいたずら書きした。 目が覚めて、皆が笑っているのを見た弁慶は、この井戸に顔を映してそのわけを知り、激怒し、喧嘩となった。 その喧嘩がもとで、堂塔を焼き尽くしてしまったという。 | ||||
 |
<<書写山円教寺:奥の院>> 三之堂のさらに西に、奥の院と呼ばれる一角がある。 開山堂を中心に、不動堂・護法堂・護法堂拝殿などが並んでいる。 大木に囲まれて、鬱蒼とした雰囲気があふれている。 | ||||
 |
<<書写山円教寺:護法堂>> 円教寺の守護神である、乙天と若天を祀っている。 乙天は不動明王の化身であり、緑の神であり、右側の社に安置されている。 若天は毘沙門天の化身であり、赤の神であり、左側の社に安置されている。 二神は、性空が円教寺を建立し、書写山で修業を始めたときに、それを助けたとされ、 以降、守護神として重要な役割を果たしてきた。 | ||||
 |
<<書写山円教寺:開山堂>> 開祖である性空が入滅した、寛弘4年(1007年)に、その遺骨を祀るために建立された。 現在のお堂は、寛文11年(1671年)に再建されたものである。重要文化財。 軒下の四隅に左甚五郎作と伝えられる力士の彫刻があるという。 | ||||
 |
<<書写山円教寺:和泉式部歌塚>> 開山堂のわきには、和泉式部の和歌にちなんだ歌塚がある。 暗きより 暗き道にぞ 入りぬべき 遥かに照らせ 山の端の月 悟りへの導きを願う釈教歌と言われ、性空は次の歌を返している。 日は入りて 月まだ出ぬ たそがれに 掲げて照らす 法の燈 | ||||
  |
<<書写山円教寺:金剛堂>> 奥の院から展望公園に入ると景色が明るくなる。 多くの紅葉が赤く色づき、地面を埋めている。 性空が書写山で修業を始めたとき、この場所にあった普賢院の塔頭に住んでいた。 室町時代には天台宗の中心となる仏である金剛薩捶菩薩像が祀られた。 現在の建物は、天文13年(1544年)の建立。 展望公園の先まで行ったのだが、立ち木に遮られて、見晴らすことができず。 <<書写山円教寺:鐘楼>> 鐘楼は、元弘2年(1332年)の再建。重要文化財 鐘は、元亨4年(1324年)の鋳造。 |