2022年9月16日
道後温泉で一泊。遍路とは言いつつ、贅沢をしている。 幸いにも、天候には恵まれている。今のところ、台風の影もない。 今日は、松山から今治に向かう。札所の間隔が短いので、数多く回ることができる。

<<圓明寺:大師堂の屋根瓦>>
|
2022年9月16日 道後温泉で一泊。遍路とは言いつつ、贅沢をしている。 幸いにも、天候には恵まれている。今のところ、台風の影もない。 今日は、松山から今治に向かう。札所の間隔が短いので、数多く回ることができる。 |
 <<圓明寺:大師堂の屋根瓦>> |
 |
<<太山寺(たいさんじ):仁王門(二の門)>> 四国霊場第52番札所 瀧雲山太山寺。 山間に分け入り、簡素な門をくぐって参道に入り、途中、二の門脇を通り、納経所脇の駐車場に車を入れる。 この先の二の門近くにも駐車場があるのだが、どっちみち納経所に立ち寄らねばならないのでここに停めることにする。 二の門は、嘉元3年(1305年)再建。重要文化財。 | ||||
   |
<<太山寺:四天王門(三の門)>> 石段の先には立派な三の門がそびえる。 天和3年(1683年)の再建。四天王門。 この寺には、「一夜建立の御堂」の伝説がある。 用明2年(587年)、豊後国臼杵の真野の長者という者が、船で浪速に向かうとき、高浜の沖で大嵐にあった。 観音さまに無事を祈願したところ、山頂から光が差し嵐が静まり、無事高浜の岸に着くことができた。 この報恩にと一宇の建立を大願し、豊後の工匠を集めて本堂を建てる木組みを整えて船積みした。 順風をうけて高浜に到着、夜を徹して組み上げ、燦然と朝日が輝くころに本堂は建ち上がった。 いらい「一夜建立の御堂」と伝えられている。 <<太山寺:本堂>> 嘉元3年(1305年)の建立。国宝。 天平11年(739年)、聖武天皇の勅願をうけて、僧行基が十一面観音像を彫って本尊にした。 孝謙天皇(在位749年-758年)の頃には、七堂伽藍と66坊を数えるほどの壮観であったという。 天長年間(824年-834年)に、弘法大師が訪れ、それまでの法相宗から真言宗に改宗している。 本尊は、十一面観音。 ただし平安時代末の作。重要文化財。 <<太山寺:大師堂>> 明治17年(1884年)再建。 本堂より一段高いところに大師堂が建てられている。 | ||||
 |
<<太山寺:大師堂の天井絵>> 大師堂の天井には、数多くの絵が描かれている。 | ||||
 |
<<太山寺:境内>> 本堂の周りには、三の門を初め、鐘楼や、茶堂、護摩堂などが立ち並んでいる。 | ||||
 |
<<太山寺:大日如来>> 三の門の石段下に、大日如来を初めとする石像群がある。 | ||||
 |
<<圓明寺(えんみょうじ):山門>> 四国霊場第53番札所 須賀山圓明寺。 天平勝宝元年(749年)、聖武天皇の勅願を受けて僧行基が本尊阿弥陀如来を刻んで開基した。 当初は現在地より北西約2.5kmの海岸にあり「海岸山圓明密寺」と称していた。 後に弘法大師が荒廃した諸堂を整備して、札所として再興した。 鎌倉時代に度重なる兵火で衰微したが、元和年間(1615年-1624年)に土地の豪族須賀重久によって現在地に移された。 | ||||
 |
<<圓明寺:中門>> この寺には中門がある。 中門をくぐって本堂があり、中門の前、左側に大師堂がある。(右は観音堂) まさに、境内の中心に中門がある感じ。 | ||||
 |
<<圓明寺:本堂>> 本尊は、阿弥陀如来。絶対秘仏。 前立の阿弥陀如来が拝観できる。 天井近くには、左甚五郎作と伝わる龍の飾りがある。 | ||||
 |
<<圓明寺:大師堂>> 大師堂の天井は、数多くの絵で埋め尽くされている。 丁度、小学校の遠足の一行が現れ、境内を埋めてしまった。 ちょっと、写真を撮る環境でなくなった。 | ||||
 |
<<圓明寺:大師堂の屋根瓦>> 大師堂の屋根がすごいことになっていた。 正面には翼を広げた龍が立ち、その左右の足元には虎が控えている。 棟瓦にも、数体の龍が身をくねらせている。 本堂の瓦も、充分に意匠が凝らされているのだが、ここはその数倍も凝っている。 やりすぎ感さえある。 一帯、どうしてこうなったのか? | ||||
 |
<<圓明寺:キリシタン灯籠(マリア観音)>> 大師堂の脇を奥に入ったところにひっそりとマリア観音と言われる石像が立っている。 それと記しがなければ、通り過ぎてしまうだろう。 どのような謂れがあるのかわからぬが、昔から当地にあったらしい。 禁教と知りつつ、寺の方でも、黙認していたらしい。 この札所で松山市の八カ寺(46番浄瑠璃寺から53番圓明寺)が終了する。 | ||||
 |
<<延命寺(えんめいじ):仁王門>> 四国霊場第54番札所 近見山延命寺。 養老4年(720年)、聖武天皇の勅願を受けて僧行基が本尊不動明王像を刻み、現在地の北、近見山の山頂に堂宇を建て開基した。弘仁年間(810年-824年)、嵯峨天皇の勅願で空海が堂宇を再興、不動院圓明寺として祈願所にした。 再三、戦火に焼かれ、享保12年(1727年)に現在の地に移転した。 明治初期の神仏分離によって札所の整理があり、隣の圓明寺と同じ名前を避け「延命寺」とした。 | ||||
 |
<<延命寺:山門>> 元々は今治城の城門の一つで、天明年間(1781年-1789年)の建造とも言われる。 明治初期に今治城が取り壊されたときに、当寺に譲り受けたという。 | ||||
 |
<<延命寺:本堂>>
| ||||
  |
<<延命寺:大師堂>> 本堂から一段上がった高台に大師堂がある。 石段を覆っているのは馬酔木の木。 本堂の正面の屋根の飾りが気になる。 軒先で初めて見るような瓦だ。 
何をかたどっているのだろうか?宝珠の形ではあるが。 桃のような気もする(ももクロのマスコットのモモタンに似ているが)。 調べたところ、道後温泉の湯玉と呼ばれるものらしい。左右の渦巻きは湯をかたどっているのかな。 愛媛地方でよく見かけられ、民家の屋根にもあるそうだ。 | ||||
 |
<<延命寺:納経所のベンチ>> 大体の札所には、このベンチが置いてあるらしい。奥さんに言われて、はじめて気づく。 
| ||||
  |
<<南光坊(なんこうぼう):山門>> 四国霊場第55番札所 別宮山南光坊。
山門は、平成10年(1998年)の再建、中の四天王像は平成14年(2002年)に安置された。 まだ新しいので、金線がまぶしい。 推古天皇2年(594年)、勅により瀬戸内海の大三島に、遠土宮(おんどのみや:大山祇神社の前身)が造立された。 その後、大宝3年(703年)、国司越智玉澄が、海を渡る際に風雨によって祭祀がおろそかになることを憂い、 文武天皇の勅を奉じて、当地に勧請し、別宮と称して奉祭した。 また、本宮の法楽所として24坊を設立した。その一つが南光坊である。 | ||||
  |
<<南光坊:本堂>> 正治年間(1199年-1201年)、大三島の24の僧坊のうち、南光坊を含む8坊が別宮の別当寺大積山光明寺の塔頭として移された。 天正年間(1573年-1592年)、に伊予の全土を襲った兵火により八坊すべて焼き払われた。 慶長5年(1600年)、藤堂高虎が今治藩主に任ぜられると、8坊のうち南光坊のみを再興した。 明治初頭、神仏分離令にしたがう形で、別宮から札所を受け継ぎ分離独立し、 大山積神の本地仏であった大通智勝如来(だいつうちしょうにょらい)を南光坊の本尊とした。 太平洋戦争最末期の昭和20年(1945年)8月、空襲により大師堂と金比羅堂を残して焼失した。 本堂は、昭和56年(1981年)の再建。 本尊の、大通智勝如来は、本堂再建時に造られ、本堂内に安置されている。ただし秘仏。 | ||||
 |
<<南光坊:大師堂>> 大師堂は、大正5年(1916年)の建立。 太平洋戦争最末期の空襲でも焼失をまぬかれた。 四国霊場の中で「坊」とつく寺院は、この南光坊だけである。 | ||||
 |
<<泰山寺(たいさんじ):参道入口>> 四国霊場第56番札所 金輪山泰山寺。 かつて泰山寺周辺は、蒼社川(そうじゃがわ)が毎年のように氾濫し、人々から「人取川」と恐れられていた。 弘仁6年(815年)に当地を訪れた弘法大師は、村人から事情を聴き、ともに堤防を築いて加持祈祷を行ったところ、 延命地蔵菩薩を感得し、治水が成就した。 | ||||
 |
<<泰山寺:本堂>> 大師は、この修法の地に「不忘の松」を植えて、感得した地蔵菩薩の尊像を彫造して本尊とし、 堂舎を建てて「泰山寺」と名づけた。 本堂は、安政元年(1854年)の再建。 本尊は、地蔵菩薩、室町時代の作という。 境内は、まるで城郭のような石垣に囲まれている。 | ||||
 |
<<泰山寺:大師堂>> 昭和60年(1985年)落慶。 | ||||
 |
<<泰山寺:不忘松>> 弘法大師の御手植えの松は、すでに枯れてしまったが、現在は、三代目の松が枝を広げている。 | ||||
   |
<<栄福寺(えいふくじ):参道入口>> 四国霊場第57番札所 府頭山栄福寺。 駐車場の脇から境内に入る。左にはお願い地蔵、右には鐘楼。 参道を折り返すと、奥に本堂、右に大師堂がある。 弘仁年間(810年-824年)、嵯峨天皇の勅願により、この地に立ち寄った弘法大師は、 周辺の海で海難事故が相次いでいたため、海上の安全を祈願をしたという。 すると修法満願の日に、海上から光が射し阿弥陀如来が出現した。 大師は、その姿を刻して本尊として、お堂を建てて安置したという。 <<栄福寺:本堂>> 本尊は、阿弥陀如来坐像。秘仏。 ただし、現住職が本堂で婚礼をあげた時に開帳されたという。 本堂の回廊に古い箱車が置いてある。 昭和8年(1933年)、足の不自由な15歳の少年が、犬に引かせた箱車で巡礼に訪れ、この寺で足が治り、 松葉杖とともに奉納したものだという。 <<栄福寺:大師堂>>
| ||||
 |
<<仙遊寺(せんゆうじ):仁王門>> 四国霊場第58番札所 作礼山仙遊寺。 
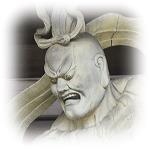
| ||||
 |
<<仙遊寺:本堂>> 海抜300mの作礼山の山頂近くに境内がある。 駐車場の大分手前に、仁王門がある。この車道は昭和中頃にできたという。 白い仁王像が印象的だ。 天智天皇(在位661年-672年)の勅願によって、伊予の大守越智守興が堂宇を建立した。 本尊の千手観音は、海から川を伝って山に登り、一刀三礼して彫った竜女の作とされる。 昭和22年(1947年)に山火事に遭い全山消失した。 | ||||
 |
<<仙遊寺:大師堂>>
| ||||
 |
<<仙遊寺:お砂踏み>> 修行大師の周りに、四国八十八カ所の本尊石仏を配し、足元に各札所の砂を埋めた石板がある。 |