2022年9月15日
松山空港に到着。レンタカーの窓口を探すのに一苦労したものの、無事にスタートすることができた。 まずは、空港の近くでお昼をとり、前回からの続きである、46番札所へ向かう。

<<八坂寺:本堂地下:万体阿弥陀仏>>
|
2022年9月15日 松山空港に到着。レンタカーの窓口を探すのに一苦労したものの、無事にスタートすることができた。 まずは、空港の近くでお昼をとり、前回からの続きである、46番札所へ向かう。 |
 <<八坂寺:本堂地下:万体阿弥陀仏>> |
 |
<<浄瑠璃寺(じょうるりじ):参道入口>> 四国霊場第46番札所 医王山浄瑠璃寺。 駐車場から境内に入った途端、鬱蒼とした木々に囲まれる。 それも、ちょっと南国風の樹木が多い気がする。 和銅元年(708年)、布教に訪れた僧行基が開山。 自ら白檀の木で薬師如来を刻し本尊とした。 その後、大同2年(807年)に弘法大師により再興される。 本尊は、薬師如来。 | |||
 |
<<浄瑠璃寺:本堂>>
| |||
 |
<<浄瑠璃寺:大師堂>> 正徳5年(1715年)に山火事で建物・本尊がすべて焼失した。 江戸時代中期に、村の庄屋井口家から仏門に入り住職となった堯音が全国を行脚して浄財を集め、 70年後の天明5年(1785年)に、現在の本堂及び諸堂を再興している。 ここから松山市内の八カ寺が始まる。 高知市を過ぎてから札所間が割と長かったのだが、これからは間隔が短くなり、多くの札所を廻ることになる。 | |||
 |
<<浄瑠璃寺:境内>> 境内には、さまざまの謂れのある、石が並んでいる。
| |||
 |
<<八坂寺(やさかじ):いやさか不動>> 四国霊場第47番札所 熊野山八坂寺。 駐車場の奥には、大きな不動尊像がある。 「いやさか不動」といい、平成17年(2005年)の建立である。 | |||
 |
<<八坂寺:山門>> 駐車場から坂道を下って山門前に戻り、改めて参拝する。 修験道の開祖・役行者小角が開基と伝えられり。 その後、大宝元年(701年)に、 文武天皇の勅願により伊予の国司越智玉興が堂塔を建立した。 一時荒廃するが、弘仁6年(815年)に弘法大師のよって再興される。 | |||
 |
<<八坂寺:本堂>> 中世には、紀州から熊野権現を勧進して十二社権現とともに祀り、修験道の根本道場として栄えることになる。 戦国時代には、兵火によって焼失し、時代に寺域が縮小され、今日に至っている。 本尊は、阿弥陀如来。 秘仏で、50年に一度、開帳される。次回は令和16年(2034年)の予定。 本堂の地下には、信者より寄進された阿弥陀如来像が並んでいる。 | |||
 |
<<八坂寺:大師堂>> 境内には、思わずほっこりする、お地蔵さんが・・。 
| |||
 |
<<西林寺(さいりんじ):仁王門>> 四国霊場第48番札所 清瀧山西林寺。 駐車場から川の土手に上って山門を撮る。 階段も坂道もない境内だとホッとする。何しろ山寺が多いので。 天平13年(741年)、聖武天皇の勅願を受けた僧行基が、 伊予国国司の越智玉純と共に、一宮別当寺として創建したとされる。 大同2年(807年)には、弘法大師が巡錫の折に当地を訪れ、今の場所に寺を移したという。 | |||
 |
<<西林寺:本堂と大師堂>> 仁王門は、天保14年(1843年)の再建。 大師堂は、平成20年(2008年)の再建。 本尊は十一面観世音菩薩。 | |||
 |
<<西林寺:水子地蔵尊>> 自然木を柱にして屋根を乗せている。
| |||
  |
<<浄土寺(じょうどじ):仁王門>> 四国霊場第49番札所 西林山浄土寺。 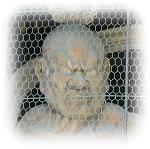

仁王像は、貞享3年(1686年)の修理の際の記録によると、運慶作とされる。 真偽はともかく、遠目で見ても迫力のある仁王像である。 <<浄土寺:本堂>> 本堂は、文明14年(1482年)の再建で、重要文化財。 本尊は釈迦如来。 | |||
  |
<<浄土寺:大師堂>> 天平勝宝年間(749年-757年)に、孝謙天皇の勅願を受けた恵明上人によって開創される。 当初は法相宗であったが、後に弘法大師が荒廃していた伽藍を再建し、真言宗に改宗した。 平安時代中期の天徳年間(957年-961年)には、空也上人が当地に3年の間滞在し、布教に努めている。 本堂内には、空也上人の像が安置されている。 伽藍は、応永23年(1416年)の兵火で焼失したが、文明14年(1482年)に、領主河野道宣によって再建された。 現在の本堂はその時に再建された建物である。 | |||
 |
<<繁多寺(はんたじ):山門>> 四国霊場第50番札所 東山繁多寺。 山門前には、両脇に大きなため池があり、満々と水をたたえている。 その向こうに、松山の市街地が広がっている。 | |||
 |
<<繁多寺:本堂>> 天平勝宝年間(749年-757年)に、孝謙天皇の勅願を受けた僧行基によって開創される。 当初は、光明寺と称していたが、弘仁年間(810年-824年)に弘法大師が寺名を繁多寺に改めたという。 時宗の開祖である一遍上人も、青年期に太宰府から伊予に帰郷した際、修行されている。 本尊は薬師如来。 | |||
 |
<<繁多寺:大師堂>> 大師像が拝観できるが、ライトアップされている。 人感センサーで制御しているらしい。お寺もハイテク?
| |||
 |
<<石手寺(いしでじ):参道入口>> 四国霊場第51番札所 熊野山石手寺。 専用の駐車場はないらしく、門前の一般の駐車場に車を停める。 仏像に限らず、多くの像が不規則に並んでいる。 仁王門までの参道が回廊のようになっていて、両側に仲見世がある。 ただ、今日は時間が遅いこともあって、ほとんど店を閉じていた。 | |||
 |
<<石手寺:渡らずの橋>> 入口には、「渡らずの橋」や、「衛門三郎」の像がある。
| |||
 |
<<石手寺:仁王門>> 仁王門は、文保2年(1318年)の建立と推定され、国宝指定されている。 仁王像は、仁治元年(1240年)頃の作で、慶派の特徴がある。重要文化財。 | |||
  |
<<石手寺:本堂>> 神亀5年(728年)、伊予の豪族、越智玉純が霊夢を見て感得し、当地に熊野12社権現を祀り、聖武天皇の勅願所となった。 翌年、天平元年(729年)に僧行基が薬師如来像を刻んで本尊として祀って開基し、法相宗の「安養寺」と称した。 弘仁4年(813年)、弘法大師が訪れ、真言宗に改めたとされる。 寛平4年(892年)、領主の赤子が当寺で祈祷を受けた際に、 握っていた手から「衛門三郎再生」と書かれた石が現れた、という衛門三郎再来の伝説によって石手寺と改められた。 本尊は薬師如来。 <<石手寺:大師堂>> このお堂の大師像は、絶対秘仏で、住職も見たことがないのだという。 | |||
  |
<<石手寺:三重塔>> 本堂、三重塔、鐘楼などは、鎌倉時代末期の建築で、重要文化財。 護摩堂(三重塔の裏)は、室町時代初期の建築で、重要文化財。
<<石手寺:大師像>> 石手寺の背後にある常光寺山(東山)の山頂に建てられている弘法大師像。 高さ16m。中国西安の方向を向いているということで、西安大師ともいう。 弘法大師(774年-853年)の千百五十年御遠忌の記念というから、昭和60年(1985年)頃の製作らしい。 | |||
 |
<<石手寺:子規句碑>> 身の上や 御鬮(みくじ)を引けば 秋の風 明治28年9月20日、病気療養中の子規が、石手寺を訪れた時に詠んだ句。 その時に御籤には、「24番凶、病は長引く」とあったという。 ここから、ほんの1kmほどで、道後温泉に着く。 子規も、温泉につかったのだろうか。 |