2022年3月19-20日
四国の八十八か所霊場は、ほぼ海岸線に沿って札所が並んでいるので、四国の中央部には、札所がない。 もっとも、山が多くて遍路できないといったほうが良いのかもしれない。
四国の中央部には、大歩危小歩危の渓谷や、仁淀ブルーで有名になった仁淀川、さらに四国カルストと呼ばれるカルスト台地などが挙げられる。 今回の遍路のついでの観光は、 現存十二天守である高知城、宇和島城と、仁淀ブルーが体験できる中津渓谷、ニコ淵とした。

<<ニコ淵>>
|
2022年3月19-20日 四国の八十八か所霊場は、ほぼ海岸線に沿って札所が並んでいるので、四国の中央部には、札所がない。 もっとも、山が多くて遍路できないといったほうが良いのかもしれない。 四国の中央部には、大歩危小歩危の渓谷や、仁淀ブルーで有名になった仁淀川、さらに四国カルストと呼ばれるカルスト台地などが挙げられる。 今回の遍路のついでの観光は、 現存十二天守である高知城、宇和島城と、仁淀ブルーが体験できる中津渓谷、ニコ淵とした。 |
 <<ニコ淵>> |
 |
<<宇和島城:藩老桑折氏武家長屋門>> 宇和島城の北側登城口の門。 藩政時代の家老桑折氏の長屋門であったものを、昭和27年(1952年)に移築した。 他の登城口としては、南側に上り立ち門がある。 形態は武家の正門とされる薬医門で、構造上は藤堂高虎の慶長期まで創建をさかのぼる可能性がある。 ただ、駐車場から遠いので、立ち寄りはあきらめる。 |
  |
<<宇和島城:井戸丸に上る石段>> 城山下駐車場に車を停め、門前で昼食をとっている間に、晴れていた空が曇ってきた。 先行きは怪しいが、雨にはならないだろうと、門をくぐる。 すぐに、石段が始まる。 宇和島城は、標高74mの丘陵とその一帯に各曲輪を配置した、平山城である。 つまり、その丘を登ることになる。 石垣の間を曲がりくねって進む。 |
 |
<<宇和島城:井戸屋形:井戸>> 城内の水場の井戸。深さ11m。 近づけないので、中は見えず。 |
  |
<<宇和島城:二の丸に向かう石段>> ほぼ残っているのは石垣のみであるため、丸亀城の山登りを思い出す。 どでも、丸亀城のほうが苦しかったような気がするが、こちらのほうが標高は高い。(丸亀城は標高66m) 真ん中に小さい石段が作られているので、登りやすい。 宇和島城は、300年以上、火災にあっていないので、古い樹木や珍しい植物が多く残っている。 石段を上っていても、森の中を歩いているようだ。 ようやく、本丸の石垣が見えてきた。 |
   |
<<宇和島城:天守閣>> 正面の天守下の石垣は、 左上半分は、隅角部「切込ハギ」、築石部「打込ハギ」であり、 右下半分は「野面積み」となっている。 この特徴から、右下半分は17世紀初頭の築城時のもので、左半分は幕末頃の修理部分と推定される。 近世城郭としての宇和島城は、築城の名手として知られる藤堂高虎によって、 慶長元年〜6年(1596-1601)にかけて築城された。 元和元年(1615年)に、伊達政宗の長子である伊達秀宗が、宇和島藩10万石に封ぜられ入城した。 二代藩主宗利は、寛文元〜12年(1661-1672)にかけて城を大改修した。 城構えは藤堂高虎のものを引き継いでいるが、岩盤上に建造した望楼型天守から、石垣造りの天守台をもつ層塔型天守に変貌を遂げた。 現在の天守はこの際のもので、現存12天守のうちの一つである。 万延元年(1860年)には、天守の大規模な改修が行われたが、 その際に作られた1/10サイズの精密な模型が、天守内で陳列されている。 そして、明治維新まで、9代にわたって、伊達家の居城として威容を誇っていた。 明治以降、周りの建物はほとんどが撤去された。 本丸跡には、現在天守閣のみが残っている。 もう少しすると、公園の桜が満開になるのだろう。ここはちょっと開花が遅れているようだ。 |
 |
<<宇和島城:天守閣から宇和島湾>> 宇和島湾が、間近に見えるが、築城時は、北側と西側の二面が、海に面しており、水城の様相を呈していたという。 その後、順次、埋め立てが進み、現在に至っている。 |
 |
<<宇和島城:天守閣内部>> 天守1階に置かれている、万延元年作成の1/10模型。 廊下の内側に障子戸がある。 また、敷居が高く作られており、障子戸の内側には畳が敷かれていたことの名残と考えられる。 |
 |
天守最上階。 |
 |
<<中津渓谷>> 高知市街地から50kmほど西に入った四国山地の山林の中に中津渓谷がある。 標高1540mの中津明神岳から流れ下る仁淀川の上流にあり、流れが硬い岩盤を削り続けたことにより形作られている。 遊歩道の入り口にあたる、中津渓谷ゆの森から下流側を見る。 右に見える人影から、岩の大きさが分かる。 |
 |
季節も間近ということで、鯉のぼりが泳いでいた。 |
 |
仁淀川の透明な流れは、なんとも言えない青く透明な水流で、仁淀ブルーの名で有名となった。 渓谷沿いには、1.6kmに及ぶ遊歩道ができている。 |
   |
遊歩道は、コンクリート製のしっかりしたもので、足元に心配はない。 ただ、上流に向かっているので、上りの階段が多い。 むしろ、岩がセリ出ているところがあるので、頭をぶつけないように注意が必要。 |
 |
<<中津渓谷:雨竜の滝>> |
 |
雨竜の滝は、落差20m。遊歩道で、真下に近いところまで近づくことができる。 今日は、少し水量が少な目なのかな。 |
 |
<<中津渓谷:龍宮淵>> 雨竜の滝の上部。何とも言えない色をしているが、これ以上近づくことはできない。 眼の先を県道が通っている。 遊歩道のあちこちに、七福神の石像が置いてある。 |
 毘沙門天 |
 恵比寿天 |
 弁才天 |
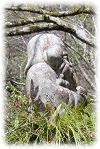 大黒天 |
 福禄寿 |
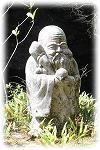 寿老人 |
 布袋和尚 |
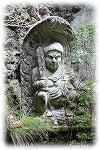 不動明王 |
  |
<<長屋沈下橋>> 沈下橋というと四万十川が有名で、どこか寄りたいと思たのだが、コースから外れており、今回はあきらめた。 仁淀川沿いで探し、長屋の沈下橋を見つけたので、立ち寄ることに。 車で近づくことができないため、道沿いに車を停め、河原に下りていく。 WEBで見つけた案内に従って、ようやく橋の袂まで行くことができた。 下流に、長屋大橋という抜水橋があるので、現在は使われていない。 片側(国道側)は、道そのものが無くなっている。 沈下橋とは、水位が低い場合には橋として使えるが、増水したときなどは水面下に沈み、橋として使えないものをいう。 特徴として、欄干がないかあっても低いもの、取り外し可能なものが多い。 対語として抜水橋があり、こちらは、増水時でも沈まない高さの橋を言う。 |
  |
<<ニコ淵>> 仁淀川水系の源流部の一つ、高知県いの町に「仁淀ブルー」の名を世に広めた神秘の滝つぼがある。 高知市の中心部から車で1時間ほど。国道194号からわき道に入る。 駐車場を心配していたのだが、多くの係員が交通整理をして、道路わきの空き場所に要領よく車を整理していた。 心配することなく車を停め、ニコ淵に向かう。 道路から階段で川岸まで降りる。鉄製のしっかりした階段ではあるが、急で段数も多く、かなりハードだ。 だが、この階段ができるまでは、はしごやロープを頼りに下りていたのだという。 階段の降り口はそれほど広くはないが、皆、ニコ淵の景観に声が出ない。 |